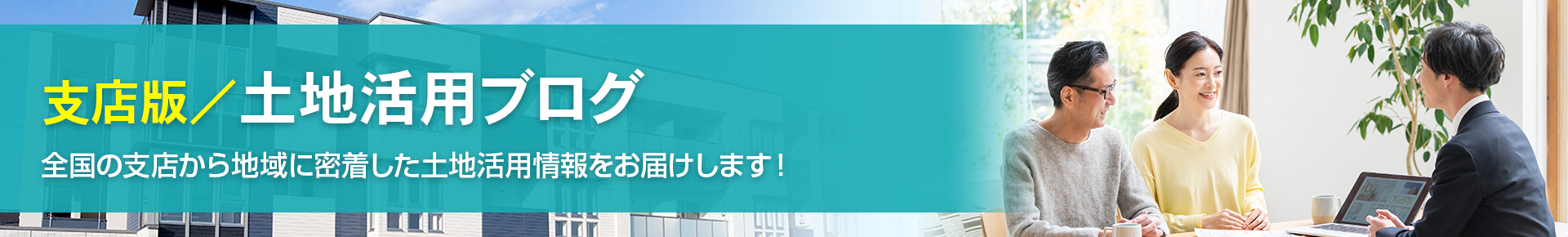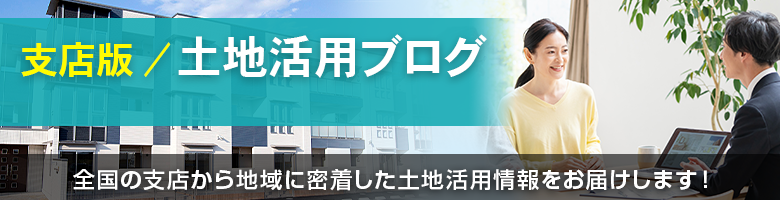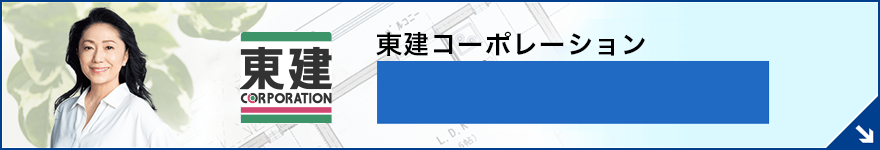松山市でベストな土地活用の選び方

松山市で土地活用をするなら、どの方法がベストなのでしょうか?
私は東建コーポレーション松山支店の営業部員です。 10年以上地主様のお話をお聞きし、最適な活用方法を考えてきたことで、たくさんの学びがありました。
特に強く思うのは、土地所有者様の状況や土地の場所・形状で、最適な土地活用の方法は変わるということです。
本記事では、松山の土地活用について毎日学び培った「松山市でベストな土地活用の選び方」について公開します。
ぜひ、最後までご覧ください。
松山市で有効な土地活用の種類

松山市の土地は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きがされています。
大まかに説明すると、以下の通りです。
・市街化区域:市街化が推奨される地域
・市街化調整区域:市街化を調整する、制限の多い地域
おすすめの土地活用方法は、大まかなエリアや詳細な場所、土地の形状等により異なりますので、松山市の市街化区域で検討できる土地活用の種類についてまとめました。
| 【1】駐車場経営 | 【2】アパート経営・戸建て賃貸経営 | |
| 【3】土地貸し | 【4】建て貸し | 【5】土地売却 |
【1】駐車場経営
駐車場経営は、建物を建てる必要がなく初期費用が少ないことから比較的はじめやすい土地活用方法です。
しかし、駐車場の土地は「事業用地」として扱われるため農地や住宅に比べて固定資産税が高くなります。
また、駐車場は歩いて通える位置に需要があり、商圏エリアが狭い活用方法です。
松山市の場合、大街道・銀天街をはじめとした松山中心エリアか、大きい企業や病院が借りてくれる見込みがない場所では注意が必要です。
【2】アパート経営・戸建て賃貸経営
アパートや戸建て住宅を建築し入居者様に部屋を貸すのが賃貸住宅経営です。賃貸住宅経営のデメリットとしては、建築費用の借入金額が大きいことと、入居仲介や建物管理・賃貸管理の業務が必要なことが挙げられます。
また、エリアや土地の形状によっては、賃貸需要がなく、向いていないことも…。
ただしメリットも大きく、正しく計画すれば収入は安定し、相続税や所得税といった税金対策の効果が大きい土地活用方法です。
東建コーポレーションでは、家賃の保証や管理も任せられるプランを用意しています。お気軽にご相談ください。
【3】土地貸し
土地貸しは、33号線や環状線など、交通量の多い幹線道路沿いで人気のある土地活用方法です。
安定した企業やお店に貸せるのであれば、初期費用をほとんどかけずに収入を得ることも可能です。
オススメの土地活用方法ですが、土地が事業用地になるため固定資産税が高くなるため、安定して借り手がつく土地でのみ検討できる活用方法になります。
【4】建て貸し
建て貸しは、建築した建物を企業やお店に貸す土地活用方法です。
収入も大きくなりやすく、節税効果も高いのが特徴です。
デメリットとしては、賃貸住宅に比べて空室期間が長くなりやすいため、安定して借り手が見込める場合以外ではおすすめできない点が挙げられます。
【5】土地売却
土地活用としては最後の手段となりますが、売却することもひとつの方法と言えます。
損得で考えるのであれば、土地の買主は買った土地で土地活用したり、形を変えて買ったりしたときよりも高い金額で売却するので、当然お得な手段とは言えません。
とはいえ、土地は所有しているだけで使っていなければ税金がかかるだけなので、家計を圧迫することもあります。
土地の価値を知るために、ご所有地で選択できる土地活用方法の確認や、土地の相場価格を知っておくことも必要と言えます。
松山市で土地活用を行う目的

土地活用を検討するうえで大切なポイントは大きく2つあります。
・その土地に合った活用方法を知ること
・なんのために土地活用をするかを決めること
特に、後者の「なんのために土地活用をするかを決めること」、つまり土地活用をする目的を明確にすることが非常に大事であることを、毎日地主様と話をする中で知りました。
以下は、土地活用を行う目的の一部です。
- ❶ 固定資産税を補いたい
- ❷ 土地を後継者に残したい
- ❸ 相続税を節税したい
- ❹ 所得税を節税したい
- ❺ 安定した収入が欲しい
❶ 固定資産税を補いたい
土地を含む不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかります。
例えば、県外に出た後継者が、親から引き継いだ実家の土地・建物。
誰も住んでいなかったとしたら収入はないので、固定資産税を持ち出しで支払うことになります。
不動産は活用しなければとマイナスにしかなりません。
こうした場合、実家の建物を壊して駐車場にするケースが多いのですが、固定資産税が高くなるので、土地に合わせた活用方法を検討する必要があります。
❷ 土地を後継者に残したい
不動産を後継者に良い形で残したいとお考えの方に、多く見られるお悩みがいくつかあります。
代表的と言えるのが下記の3つです。
・将来的に大きい相続税がかかる
・接道のない土地があり、後継者の負担になる
・農地を持っているが、後継者は農業をしない予定
土地は所有しているだけだと、固定資産税の納税や管理が必要になります。日々の営業活動の中で、後継者様から感謝されている家庭と、その逆の家庭で、それぞれのお考えをたくさん聞いてきました。
その情報から浮かび上がった、資産承継をする上で大事なポイントは2つあります。
・ご所有地で可能な土地活用の選択肢を確認すること
・後継者様に早いうちからご所有地や税金の状況を話しておくこと
相続を視野に入れて土地活用を考えると、できる対策の内容は年齢や時期によって異なります。
「相続」を「争族」にしないためにも、早すぎると思うくらいのタイミングで、後継者様に資産情報を共有することをオススメします。
❸ 相続税を節税したい
土地を所有している場合に1番多い悩みは、相続税に対する不安です。
特に、松山市の土地は相続税評価が高く、「先祖から田を継いだだけなのに、相続税が◯千万?!」なんてことも珍しくありません。
相続税の対策は、アパート経営や建て貸しなど、建物の建築を伴う土地活用をすることが一般的ですが、立地や土地の形・資産状況により、ベストな選択肢は変わります。
相続はその性質上、そう何度も経験することではありません。ぜひ、気軽に東建コーポレーション松山支店までお問い合わせください。
❹ 所得税を節税したい
アパートや建て貸しといった建物を建てて行う賃貸経営は、所得税対策としても有効です。
所得税は、所得の金額(=収入−支出−控除)から計算されます。
建物を貸す賃貸経営の場合、毎年建物の評価が下がる分の金額を「減価償却費」として支出計上することが可能です。
事業計画にもよりますが、実際の収支はプラスなのに、確定申告上はマイナスにできる可能性もあります。
不動産所得は、給料などと合算できる総合課税に分類されるため、土地活用が会計上赤字であれば、所得税を下げることができるのです。
❺ 安定した収入が欲しい
土地活用を行うことで、収入を得ることができます。収入が欲しい理由は様々ですが、具体的には下記の様な理由があります。
・老後の生活費
・子や孫の学費
・住宅ローンの補填
何度もお伝えしたとおり、土地は所有しているだけではお金を生み出せません。
土地は活用してこそ有効資産になります。高額資産である土地が、適切に活用をすることで収入を生み出してくれることは、当然のことだと言えます。
土地活用の営業として日々考えていること

冒頭で自己紹介したとおり、私は土地活用の営業部員として毎日地主様のお話を聞き、土地活用について勉強して参りました。
営業と聞くとセールスマンのイメージがわく方も多いと思いますが、実際はものを売るという考えでは仕事をしていません。ベストな土地活用は、地主様の考えや所有資産によって大きく異なります。
私達の提案は責任が大きく、自分を頼りにしてくださるお客様の幸せを考え、真剣に取り組むべき仕事です。お客様に感謝してもらえることが、1番のやりがいだと感じています。
松山市の土地活用まとめ
最後に、松山市でベストな土地活用を選択するための方法をまとめます。 土地活用を検討する際、最重要ポイントは以下の2つです。
・その土地に合った活用方法を知ること
・なんのために土地活用をするかを決めること
松山市の土地活用方法には以下のような種類があり、ご所有地にはどれが適しているかを知る必要があります。
<土地に合った活用方法>
| 【1】駐車場経営 | 【2】アパート経営、戸建て賃貸経営 | |
| 【3】土地貸し | 【4】建て貸し | 【5】土地売却 |
また、なんのために土地活用するのかを整理することで最適な活用方法を検討することができます。
<土地活用の目的>
- ❶ 固定資産税を補いたい
- ❷ 土地を後継者に残したい
- ❸ 相続税を節税したい
- ❹ 所得税を節税したい
- ❺ 安定した収入が欲しい
上記のとおり、土地活用は様々な視点から総合的に考える必要があり、私達はたくさんの事例から、地主様のニーズと、ご所有地の条件に合わせたご提案が可能です。
今日も、「あなたに会えて良かった」と言ってもらえるお客様にお会いするため、地主様とお話をしていきます。
- 松山支店
- 土地活用、アパート経営・賃貸経営に 関するご相談はこちら
-
 おうちに居ながら土地活用・賃貸経営の相談ができる 詳細はこちら弊社では、土地活用や賃貸経営についてのご相談を、オンラインまたはメールにてご対応させていただいております。パソコン、スマートフォン、タブレットを使ってご利用いただけます。
おうちに居ながら土地活用・賃貸経営の相談ができる 詳細はこちら弊社では、土地活用や賃貸経営についてのご相談を、オンラインまたはメールにてご対応させていただいております。パソコン、スマートフォン、タブレットを使ってご利用いただけます。- お電話でお問い合わせ
- フリーダイヤル0120-51-8200
- 受付時間
- 平日:9~12時、13~17時※土・日・祝日、夏季・年末年始は休業