土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る裏座敷(ウラザシキ)
「裏座敷」とは、家の奥にあり、家族や身内が主に使用する座敷のこと。反対語・対称語は「表座敷」(おもてざしき)。裏座敷が残っている住宅の中でも、国家指定文化財に指定されている物がある。例えば、愛知県にある「旧磯部家住宅」(きゅういそべけじゅうたく)の裏座敷は、国土の歴史的景観に寄与しているとして、文化財に指定されている。大正時代に造られたこの住宅には、主屋の奥の中庭を渡り廊下が通り、その先に裏座敷を配置。裏座敷は平屋になっており、8畳と5畳半の部屋が繋がった広さを持ち、屋根は「唐招提寺講堂」(とうしょうだいじこうどう)や「円覚寺舎利殿」(えんがくじしゃりでん)でも採用されている、「入母屋造」(いりもやづくり)という構造の瓦屋根になっている。柱やその上部の構造を支える桁(けた)、そして見える箇所には美しい垂木(たれき)が使用され、その外観は、シンプルでありながら、洗練された佇まいとなっている。

表座敷(オモテザシキ)
「表座敷」とは畳敷きの部屋の1種で、現代の一般的な家屋では、いちばん良い和室のことを指す。玄関に近く、客間として使用される座敷は「表座敷」という言葉が用いられ、家族が団らんする和室のことは「奥座敷」という反対語・・対称語で表される。日本古来座敷は使用されており、鎌倉時代から「書院造」(しょいんづくり)の家屋に客用の座敷が設けられて、対面したり酒宴を行なったりする部屋であった。また、もともとは武士に必要な書斎の役割を果たしていた書院が、時代が進むにつれて広い客間になっていったのである。その後、畳敷きの部屋が普及すると、座敷に豪華な「床の間」(とこのま)を配し、障子や襖の意匠にも工夫を凝らすようになった。このような座敷が、近現代の和室における表座敷に当たり、日本の旧家の遺構では、趣向を凝らした床の間や棚、「付書院」(つけしょいん)などのいわゆる「座敷飾り」が今でも見られる。





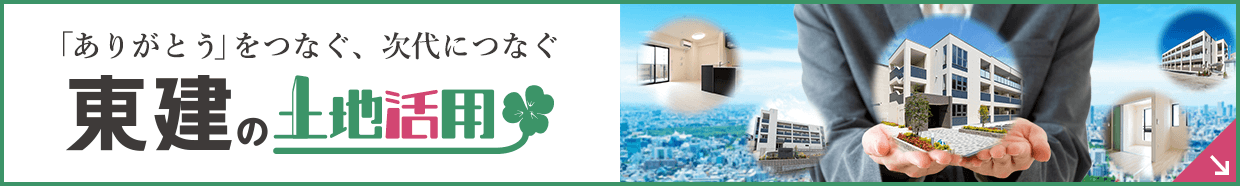

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。