土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る上張り(ウワバリ)
「上張り」とは、床や壁など既存のものに新しく床材や壁材を張り付けることを指す。反対語・対称語は「下張り」(したばり)。壁材には、サイディング(上張りに使用する外壁素材)を使用することが多いため、保温性や遮音性の向上、クラックと呼ばれるひびなどが入りにくいことがメリットとして挙げられる。さらには、以前の塗装部分をはがす工費も節約することが可能。壁材の上張りのデメリットとしては、サイディングの材料の大部分がセメントであるため、年数の経過により、塗膜が風雨にさらされてはがれると水を含むようになることや、熱を吸収しやすいので夏場の室温が上がりやすくなることが挙げられる。床への上張りは防音対策などに用いられ、現状の床にさらにゴム材を張り、さらに床材を張ることが一般的。メリットは、固体音を防ぐことができること、以前の床をはがさずに施工できるため、以前の床材をはがす手間や工事にかかわる人員を削減することができるなど、費用を抑えられる点にある。しかし、段差が生じてしまうこともあるため、以前の床に合わせたドアなどの建具を削るなどの、別の作業が必要になるデメリットも考慮しなければならない。

下張り(シタバリ)
「下張り」とは、建物内の襖(ふすま)や壁などを施工する際に、上張りの仕上げを良くするために、下地として張る布や紙のこと。また、その工程そのものを指す場合もある。反対語は「上張り」(うわばり)。基本的な一連の工程は、まず、壁紙用の接着剤を用いて下張りの紙を張り付けたあと、上から仕上げの壁紙を張り付けるというもの。下張り工法の種類は、「ベタ張り」と「袋張り」(ふくろばり)という2種類。下張り工法は、何度も重ねるほど湿気に強くなり、襖の表紙が波打つ問題を解決できて頑丈な襖になるが、その反面、価格や時間がかかる工法であるため、その回数が増えるほど高価になるというデメリットがある。また、防火性能については、直張り工法よりも若干弱い面が見られることから、防火性能が求められる施工箇所には使用することはできない。そのため、下張り工法を用いる場合は、防火対策についても施主や工事監理者の十分な協議が必要になる。





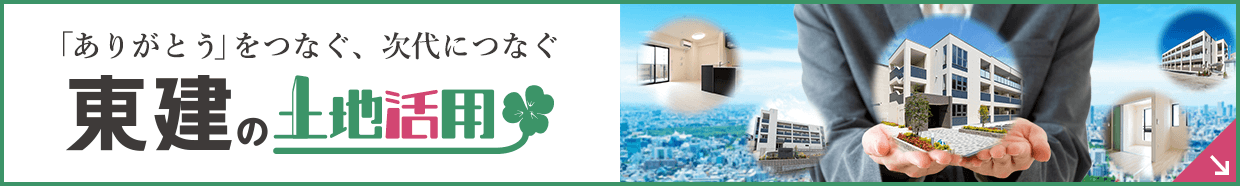

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。