土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る表書院(オモテショイン)
「表書院」とは、「書院造」(しょいんづくり)の家屋の表側に位置する客間を指す。「書院」とは、元来禅僧の居間兼書斎の機能を持つ部屋であったが、室町時代には、武士の住まいにも取り入れられるようになり、その後、接客の場に変化。その変化とともに、「床の間」(とこのま)の脇に出窓である「付書院」(つけしょいん)が設けられるなど、装飾にも趣向を凝らすようになる。これは「座敷飾り」と呼ばれ、この他にも違い棚や障子、襖絵などがあり、江戸時代、そして明治時代へと、その文化は引き継がれていった。現代の和室にも、このような書院造の要素は見られるが、古代の日本では、それぞれの身分によって書院を含む座敷の形態が異なる。また、「表書院」の対になる「裏書院」(うらしょいん)は、客間ではなく、家人が日常の事柄を行なうための書斎であり、家の奥に配置されていた。このように書院造の家屋は、「表」側は「客人」用に、「裏」側は「家人」用というように分けられていたのである。

奥書院(オクショイン)
「奥書院」とは、家屋の奥にある、近世の日本で成立した住宅様式である「書院造」(しょいんづくり)の座敷のこと。反対語・対称語は「表書院」(おもてしょいん)である。「書院」という言葉はもともと、鎌倉時代の禅宗(ぜんしゅう)の僧が住む建物にある居間兼書斎のことを指していた。そして室町時代以降、武士の邸宅がこの書院を中心にして構成されるようになり、「床の間」(とこのま)や「付書院」(つけしょいん)など、いわゆる「座敷飾り」が備えられて装飾品を配し、このような様式の建物を「書院造」と呼ぶに至る。「付書院」とは、床の間の脇に窓を設置し、板張りで机のように作られた書院の1種。書院は現代の和風建築にも用いられ、一般住宅では、床の間周辺の棚や障子で形成された一角のことを意味し、付書院も取り入れられている。江戸時代の書院は接客を中心とする「表向き」と、家の中のこまごまとした雑事を行なう「奥向き」に分かれていたことから、奥書院は家の奥に位置して日常的なことを処理する場であった。





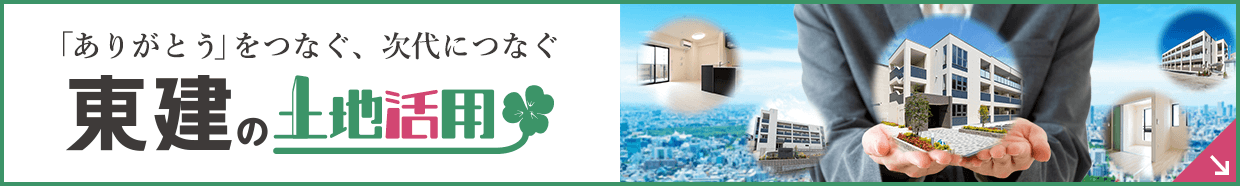

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。