土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る主柱(オモバシラ)
「主柱」とは、建造物の中心となり、地面に垂直に立ててその支えになる柱のことを指す。反対語・対称語は「袖柱」(そでばしら)で、主柱を補強するために、その両側に立てた小さな柱を意味する。日本家屋の主柱は、「大黒柱」(だいこくばしら)とも呼ぶ。建築では、柱だけでなく、梁(はり)や壁といった部材も、建物の重みを受ける重要な物。梁の役割は、屋根の最も高いところにある棟木と直角に交わり、屋根などの荷重を柱に伝えること。建築の構造図で柱を表す記号は、英語で柱を意味する「Column」(コラム/カラム)の頭文字である「C」。主柱以外にも柱の種類は多岐にわたり、例えば、2階建て以上の建物において、土台から上の階まで続く「通し柱」(とおしばしら)や、壁の補強用として、柱と柱の間に使用する「間柱」(まばしら)などがある。これらの柱や梁、壁などの配置や連結の方法が家の強度に大きくするため、家を建てるときには、構造知識が豊富な専門家を選ぶことが重要である。

袖柱(ソデバシラ)
「袖柱」とは建築物を支える柱の1種で、建築物の中心となる「主柱」(おもばしら/しゅちゅう)の左右、もしくは前後に設置され、主柱を補強する役割を担う。袖柱は、長さは主柱よりも短く、主柱と袖柱を繋ぐ横木となる部材のことを「貫」(ぬき)と呼ぶ。橋や神社の鳥居、寺院の門などに設置される「袖柱」の類語には、「稚児柱」(ちごばしら)や「控え柱」(ひかえばしら)というものがある。奈良時代から存在していると推測される「四脚門」(よつあしもん/しきゃくもん)にも袖柱が設けられており、由緒ある建築物の正門に据えられるケースが多い。また、「袖柱」のある鳥居は「両部鳥居」(りょうぶとりい)と称され、別名「四脚鳥居」(よつあしとりい)、「権現鳥居」(ごんげんとりい)とも言う。両部鳥居の代表例には、重要文化財に指定されている「厳島神社」(いつくしまじんじゃ:広島県廿日市市[はつかいちし])の大鳥居(おおとりい)がある。





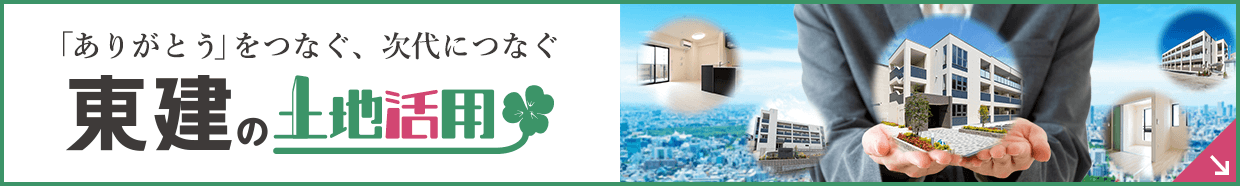

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。