土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る共同相続(キョウドウソウゾク)
「共同相続」とは、相続人が2人以上いる相続形式。1947年(昭和22年)、新憲法に伴って民法が改正される前の日本では、古くからの慣習である「家督相続」が主流であったため、「共同相続」の反対語・対称語となる「単独相続」の考え方が通常であった。民法改正により家督相続が廃止され、法定相続をベースとする共同相続が原則となる。家督相続は、戸籍上の戸主が死亡、または隠居すると、その家の長男がすべての財産を相続する制度。身分が相続され、かつ相続放棄もできないことが、共同相続との大きな違いである。法定相続では男女は問わず被相続人が死亡するとすぐに、相続財産が概念的に相続人の共有するものとして認識され、相続人の人数や被相続人との関係によって相続分が計算されて分配されるが、この特殊な概念を解消して、各相続人が単独の相続人となる手続きを行なうことを「遺産分割」と言う。

単独相続(タンドクソウゾク)
「単独相続」とは、亡くなった人が残した財産のすべてをひとりの相続人が継承すること。反対語・対称語は「共同相続」(きょうどうそうぞく)で、2人以上の相続人が遺産を継承する形を取ることを意味し、現在はこちらが原則。配偶者は常に相続人であり、配偶者の次に相続人になれる人は、順に「子ども(子どもが亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっていればひ孫)」、直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母、祖父母など直系血族のうち、被相続人より上の世代)、「兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥、または姪)」と定められている。遺言書で特定のひとりに相続させる旨の記載があった場合、その人が最優先の相続人となって単独相続が可能。しかし、順位が定められた法定相続人のうち、兄弟姉妹を除いた相続人には「遺留分」(いりゅうぶん:法律上、一定の相続人のために残しておく必要のある遺産の割合)を請求できる権利「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」があり、これを行使する意思が示されれば、単独相続はできない。





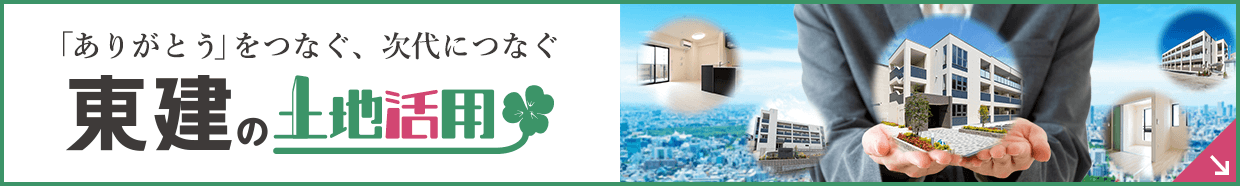

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。