土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る小間(コマ)
「小間」には、「少しのあいだ」、「短い時間」という意味があるが、住宅や建物に用いる場合は、「小さな部屋」、あるいは「狭い部屋」と意味を示す。反対語・対称語は「大間」。また、一般的な茶道を行なう際にも、「小間」が使用される。その場合は、4畳半よりもやや狭い、小さな部屋を指す。また、茶道においても茶室1室の大きさを示すのに用いられる言葉で、その場合の「小間」は、4畳半以下の茶室のことを意味する。それに対して、4畳半以上ある場合は「広間」(ひろま)という。また、木造などの建築物の構造においても用いられ、その場合の「小間」は、屋根板を支えるため、棟(むね)から軒(のき)に斜めに渡される「垂木」(たるき)同士のあいだや、床板を支える補強材である「根太」(ねだ)と根太のあいだのことである。

大間(オオマ)
「大間」とは別名「京間」(きょうま)・「関西間」(かんさいま)と言い、日本建築における関西方面の間取りに関する尺度を指す。柱割り(はしらわり:平面の間取りで柱の位置を決める方法)を基準とすると、1間(いっけん)は柱間(はしらま:柱と柱の空間)が6尺5寸(1,970mm)、畳の寸法が6尺3寸(1,910mm)となる。それに対して、畳割り(たたみわり:一定の畳の寸法を基準にして住宅の平面を決定し、柱の位置を決める方法)を用いる方法もあり、この場合は、畳の寸法は6尺5寸×3尺1.5寸(955mm)。関東方面と関西方面では、間取りの基本となる畳1畳の大きさは基準が異なる。東日本全般で使用される、「江戸間」(えどま)と呼ばれる畳は、「五八間」(ごはちま)や「関東間」(かんとうま)とも言われ、寸法は 5尺8寸(1,760mm)×2尺9寸(880mm)。このように、同じ畳であっても地方によって寸法が変わることから、引越しなどの際、間取図の畳の数だけで部屋を想定すると、家具が入らないなどの問題が起こってしまう。そのため、できれば部屋を直接目で見て確かめ、具体的な家具の採寸などを行うことは大切である。





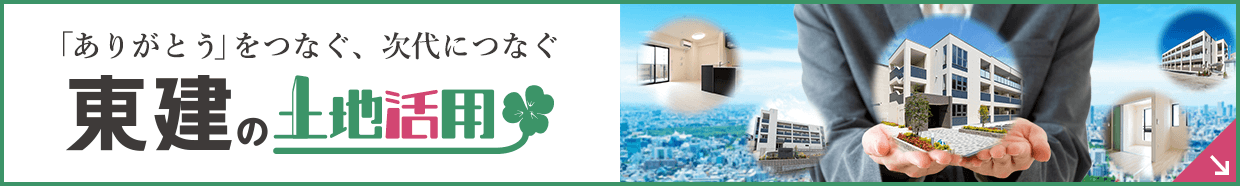

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。