土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る単板(タンバン)
「単板」とは、原木を薄く(0.2〜6mm前後)切り削ってできた板のこと。1枚の板のみで構成される、いわゆる「一枚板」のことで「ベニヤ」とも言う。建築物の内装や家具などに使われる単板は、「化粧単板」「ツキ板」(同音で「突き板」「突板」とも表記する)と言い、0.2〜0.6mm程度の物が多い。ツキ板は、表面を覆うための単板であるため、キリ、スギ、ヒノキ、ケヤキ、オーク、マホガニーなどの色合いが美しい木を使用。また、単板面の木目には、年輪が平行に現れて反りや収縮が少ない「柾目」(まさめ)、山形やたけのこ形など、不規則な波形の木目が現れる「板目」(いため)などの種類があり、複数枚の単板を、木目の方向が交互に直交するように重ね合わせた板材を「合板」(ごうはん/ごうばん)と呼ぶ。単板、すなわち「ベニヤ」を貼り合わせて加工していることから「ベニヤ板」とも言われることも。合板用の単板は、主に1〜4mmほどの厚さに作られ、その原産は、熱帯アジアの広葉樹材が使われることが多かったが、近年では、国産の針葉樹材の割合も増加している。

合板(ゴウハン)
「合板」とは、原木を大根のかつらむきのように一定の厚さでむいた物を、木目の縦目と横目が交互になるように奇数枚重ね、接着剤で貼り合わせてつくった板のこと。このとき、一定の厚さでむいた板のことを単板(ベニヤ)と呼び、単板を貼り合わせる枚数で「合板」の厚さは変わる。薄くむいた木材を貼り合わせる技術は、紀元前の古代エジプト時代からあり、1870年ごろにヨーロッパで単板を切り出す機械・ベニヤレースが開発された。日本では1907年(明治40年)に、浅野吉次郎という人が独自に開発したベニヤレースが実用化され、以降「合板」が多く使われるようになったとされる。重さのわりに強度があり、加工の自由度が高く、広い面積の板が得られることなどが「合板」の特徴。「合板」の用途は建築土木から家具、工芸品など多岐にわたり、楽器、黒板、事務用品など生活に密着した様々な物にも活用されている。





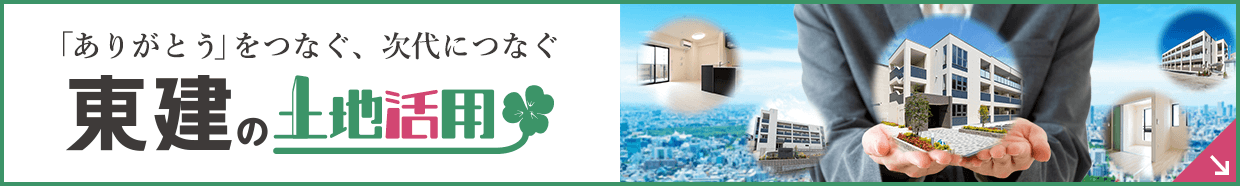

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。