土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る平屋(ヒラヤ)
「平屋」とは、建築物を構成する階数の1区分であり、1階のみで建てられた家のことを指す。「1階建て(いっかいだて)」を意味する言葉で、「ひらや」と読む。別の表記には「平家」がある。1層の床や壁などの単純な建築構造のため、部材のコストを抑えることができ、様々な建築物に使用されている。住宅メーカーからも売り出されるなど、再び注目されるように。2階建てよりも少なくて済む部材のため、1965年(昭和40年)頃までは多くの住宅が、簡単な間取りの「平屋」を採用していた。リフォームの際、増改築の自由度は高く、リノベーションされた「平屋」は「フラットハウス」と呼ばれている。階段を備えないワンフロア住宅は、高齢者が生活しやすい住宅である。

二階屋(ニカイヤ)
二階屋とは、二階建ての家すなわち、二階があるつくりの家のことである。地表から上下2層の階のある建物で「二階家」とも書く。建物の中には「平屋」(平屋建て)があるが、これは地面の真上に床・外壁・天井で作られた住居のことで、この上に近接して床・外壁・天井を作り屋根を付けた建物が二階屋である。二階建ての最大のメリットは、限られたスペースで広く暮らせる住まいを作ることができる点。他にも、プライバシーの確保やセキュリティーの面においても、平屋より強みがあると言える。しかし、平屋と比べて階段の上り下りや掃除が大変であるというデメリットも。一階、二階の面積がほぼ同じに建てられた「総二階」と呼ばれる建物は、この二階建てのメリットが最大限に活かされた物である。二階屋の歴史は古く、京町屋は江戸〜明治、大正、昭和初期にかけて、厨子二階(つしにかい)、仕舞屋(しもたや)、総二階(本二階)、昭和初期型など様々な外観の二階屋が建てられた。また、佐渡市の二階屋旅館は江戸時代に造られた歴史ある二階建て建築として有名である。





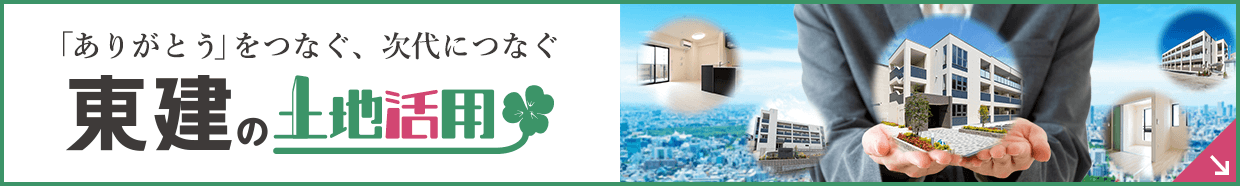

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。