土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る床下(ユカシタ)
「床下」とは、家屋の基礎部分から床の下までのことを言う。床下は英語で「Floor bottom」「under the floor」と表記する。木造住宅の場合、床下は湿気がこもりやすい場所になっているため、建築基準法では換気口を作らなければいけない。しかし、一部換気対策をされている住宅は免除になる。「床下」の反対語として「床上」があり、大雨などで浸水した場合に床の上まで浸水したときは床上浸水、床の下まで浸水したときは床下浸水と言う。床下の修理や点検を目的として家屋の基礎部分に入れるように、「床下点検口」が設けられている家もある。また、床下と基礎部分のデッドスペースに「床下収納庫」を設けている家もあり、キッチンや洗面所、和室など場所によって収納する用途が変わってくる。

床上(ユカウエ)
床上とは、建物の床(ゆか)の上のことである。「ゆかうえ」または「しょうじょう」と読む。対して床の下、縁の下のことを「床下(ゆかした)」と言う。床とは、建物の内部にあり、そこに住む人間が歩いたり座ったり寝転んだりする場所である。地面より高い位置に水平に板張りを施した所、またはその上に畳などが敷かれた所を言う。住宅の床の高さは、木造で45cm以上と建築基準法で規定されている(地面からの水蒸気による床下構造部の腐食を防止する措置が施された場合を除く)。原始時代には床のある住居は存在せず、土間でそのまま暮らしていた。日本で床の住居が発達してきたのは奈良時代である。上流階級の人々が住居内に板張りの床を張り、履物を脱いで床の上で暮らすように。室町時代になると板張りの上に畳を敷き詰めるようになり、こうして日本人の床への意識は強まってきた。「床上浸水」「床上まで水に浸かる」などと表現することがあるが、これは大雨や洪水などの災害時に、住宅の床の上まで水が流れ込んでくることを指している。床上までは水に浸かっていないが、床の下に水が流れ込むことを「床下浸水」と言う。





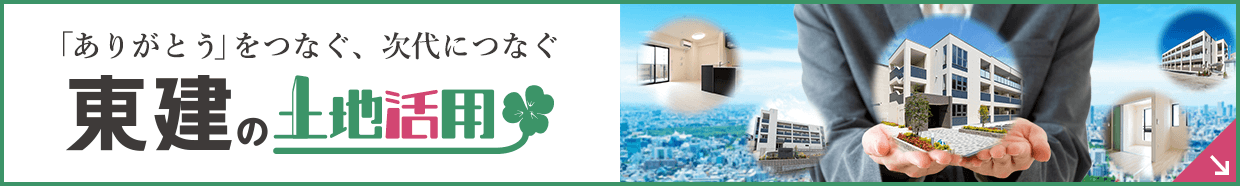

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「住まいの反対語・対称語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりやすく解説しているため、初めて目にする方も安心してご利用頂けます。また住まいの反対語・対称語辞書以外にも建築用語辞書や不動産用語辞書などご活用できる用語辞書を数多く集めました。お調べになりたい専門用語があるときにご利用頂けます。