「火災保険」をかける際のポイント
アパート経営をする上で、必ず入っておきたいのが「火災保険」です。火災保険は、かけ方によって補償内容が大きく異なりますので、その仕組みをよく理解した上で、保険商品を選びましょう。
火災保険とは

「火災保険」とは、火災やその他の災害などによって、建物や備品などに損害が生じた場合に、その損害を補償することを目的とした保険です。補償の範囲や内容は、対象となる物件の種類や各保険会社によって異なります。
なお、アパートの建築資金を金融機関からの融資で調達する場合は、火災保険の加入が必須条件となります。
※地震により、建物に損害が生じた場合には、保険の対象外となります。補償を受けるためには、
別途「地震保険」に加入する必要があります。(後述)
保険金額を決める際のポイント
火災保険の保険金額(契約金額)は、再調達価額(新価額)をもとに決定するのがポイントです。
再調達価額(新価額)とは、同等のものを新たに建築、または購入するのに必要な金額のことです。
仮に時価をもとに時価限度額で火災保険を契約したとすれば、実際には年月の経過によって建物の価値は再調達価額よりも下がるので、同じ建物を新たに建築することはできません。それに対して、再調達価額をもとに支払われる火災保険を契約すれば、火災保険の保険金のみで建て直すことができます。
契約の際に、再調達価額(新価額)いっぱいに契約金額を設定しておけば、万一の場合に、その額を基準に契約金額を限度として損害額が支払われることになるため、安心でしょう。
「再調達価額契約」と「時価契約」の違いの例

「家賃補償特約」を利用する
万が一、火災が発生してしまった場合、火災保険に加入していれば建物に対しては一定の補償が受けられますが、建替えまでの間の家賃収入は補償されません。
そのため、火災発生時における家賃の損失に備えて、火災保険の特約のひとつである「家賃補償特約」という商品があります。
家賃補償特約の内容と支払金額
| 家賃補償特約の 内容 |
契約時に定めた家賃補償期間(約定復旧期間)の範囲で、火災保険によって建物を元通りに再築するまでの間に発生する、家賃の減収額が支払われる。 |
|---|---|
| 支払金額 | 建物の家賃月額に、家賃補償期間を乗じた金額が支払金額となる。ただし、水道・ガス・電気などの使用料や権利金・礼金・保証金(敷金)などの一時金などは、家賃に含まれない。 |
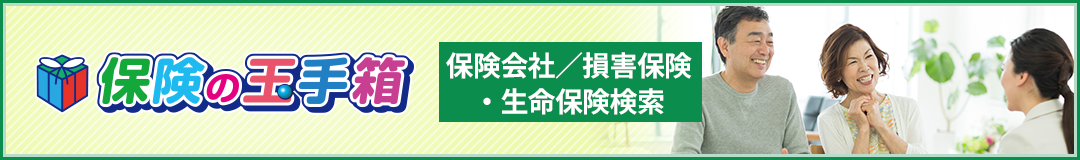







東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験と培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド アパート経営編」の「土地活用 アパート経営の基礎知識」から「アパート経営に必要な保険」について紹介。災害リスクの備えとして「火災保険」や「地震保険」といった損害保険が存在します。万が一のために加入しておくべき保険をご確認下さい。