- 文字サイズ
- 小
- 中
- 大

何の利用もされていない土地を「遊休地(ゆうきゅうち)」と呼びますが、土地を遊休地のまま放置すると、様々なデメリットが生じてしまいます。
一方、土地を有効に活用することができれば、デメリットは解消され、収益を得られるなどのメリットを享受することができます。
この記事では、遊休地を放置するデメリットや活用するメリットをはじめ、遊休地を活用する際におすすめの土地活用を、土地の状況に応じて10選ご紹介します。
目次
1.遊休地(ゆうきゅうち)とは

まずは、「遊休地」の定義について確認してみましょう。
また、「遊休土地」や「更地」、「整地」といった、遊休地と似た土地との違いについても解説していきます。
1-1.遊休地の定義
「遊休地」とは、住宅や農地、駐車場など、あらゆる用途で活用されずに放置されている土地のことです。
そのため、たとえ砂利敷きやアスファルト舗装がされた土地であっても、実際には何の用途にも活用されていない土地であれば、それは遊休地ということになります。
遊休地は、相続によって土地を取得したあとや、区画整理のあと、耕作者がいなくなった農地、何かしらの建物を建設する計画が頓挫した場合などに生じることが多いと言えます。
1-2.「遊休地」と「遊休土地」の違い
遊休地に極めて似た言葉に、「遊休土地」があります。
遊休土地は、「何の用途にも利用されていない」点は遊休地と同じですが、言葉の意味は異なります。
例えば、遊休地が「一般用語」であるのに対し、遊休土地は国土利用計画法で定められた「法律用語」です。
遊休土地は法律用語であることから、法律による明確な定義が存在しています。
具体的には「国土利用計画法に基づく土地取引の許可または届出がされた土地であること」、「取得後2年以上利用されていないこと」、「都道府県知事がその利用を促進する必要があると認めた土地であること」の3点です。
単に利用されていない土地というだけでなく、一定の要件を満たし、かつ都道府県知事によって利用が促されるべきと判断された土地が「遊休土地」となります。
一方、一般用語である「遊休地」には、法的な定義は存在しません。
1-3.「遊休地」と「更地・整地」の違い
更地とは、建物や構築物が一切なく、借地権といった土地の利用を制限するような権利が付着していない土地を指す用語です。
遊休地と更地は、意味合いが似ているため、同じ土地を指して使われることも多いです。
遊休地と更地の違いとしては、構築物の有無があります。例えば、アスファルト舗装が施されている土地は、一般的に更地とは言いません。
一方、アスファルト舗装がされている土地であっても、何の用途にも使われていない土地であれば、その土地は遊休地と呼ばれます。
また、遊休地が「何も利用されていない」という意味で用いられるのに対し、更地は「何にでも使える」という意味合いで用いられることが多いという、ニュアンスの違いもあります。
更地と似た言葉には「整地」がありますが、整地とは、凹凸や傾きがない平らな土地のことを指す言葉です。
更地が「土地の上」の現況を指す言葉であるのに対し、整地は「土地そのもの」の現況を指す言葉ということになります。
《 遊休地と類似した土地名称の違い一覧表 》
遊休地に似た名称ごとの違いを、一覧表にまとめました。
| 項 目 | 遊休地 | 遊休土地 | 更 地 | 整 地 |
|---|---|---|---|---|
| 定 義 | あらゆる用途で活用されずに放置されている土地 | 国土利用計画法で定められた、利用促進が必要な遊休地 | 建物や構築物がなく、権利関係もクリアな土地 | 凹凸や傾きをなくして平らな状態にした土地 |
| 関連する 法律 |
なし | 国土利用計画法 | なし | なし |
| 建物や構築物の有無 | どちらでもよい | どちらでもよい | ない | どちらでもよい |
| 土地の利用を制限する権利の付着 | 問わない | 問わない | 土地の利用を制限する権利が付着していない(※) | 問わない |
| 土地の状態 | 問わない | 問わない | 建物や構築物がない | 凹凸や傾斜がなく平ら |
| 利用状況 | 利用されていない | 利用されていない | 問わない | 問わない |
| 行政の関与 | なし | あり (都道府県知事による利用の促進) |
なし | なし |
※土地の利用を制限する権利に、「抵当権」や「根抵当権」は含まれません。
2.遊休地を放置するデメリット

遊休地を放置することには、次のようなデメリットがあります。
2-1.土地が荒れ、ゴミが散乱する恐れがある
遊休地を放置するデメリットのひとつは、土地が荒れ、ゴミが散乱する恐れがあることです。
遊休地は、1年も放置すると雑草が生い茂り、場合によっては害虫の住処になってしまうこともあります。
土地が荒れると、そこへゴミを捨てることへの抵抗感が薄れるため、ゴミを投げ捨てる人が現れる確率も増加します。
雑草により視界が遮られ、ゴミが捨ててある土地は、さらにゴミが捨てられやすくなる悪循環に陥ります。
その結果、最初は空き缶程度だったのが、冷蔵庫などの大型家電、廃自動車等と、処分が困難なものまでも投棄されてしまう可能性が出て来ます。
こうして土地が荒れ果て、ゴミが散乱すると、近隣住民にも迷惑をかけることとなります。その結果、自治体に近隣住民からの苦情が寄せられ、土地所有者様が行政からの指導を受けることになるケースも考えられます。
2-2.管理をする手間やコストがかかる
土地が荒れ、近隣住民の方達の迷惑にならないようにするには、小まめに草刈りをしたり、柵を立ててゴミの投棄を防いだり、定期的に巡回をする必要があります。
しかし、遊休地を管理するには手間やコストがかかります。しかも、そのコストは「お金を生まないお金」です。
管理を行った場合でも、「遊休地をそのまま所有し続けるという状況」を放置することで、デメリットが生じ続けると言えます。
2-3.高額で経費化できない固定資産税の負担が生じ続ける
遊休地を放置することには、高額で経費化できない固定資産税の負担が生じ続けるという点もデメリットです。
遊休地には、固定資産税を軽減する特例がなく、固定資産税を経費計上することもできないためです。
例えば、賃貸住宅経営を行っている土地や、自宅敷地であれば、「住宅用地の特例」により固定資産税を6分の1に軽減することができます。
しかし、住宅用地ではない遊休地には住宅用地の特例は適用されません。
また、土地活用を行っている土地であれば、固定資産税は事業のための必要経費として計上できるため、所得を抑え、所得税を節税することができます。
しかし、働いていない土地である遊休地には、そもそも必要経費という概念がありません。
そのため、遊休地をそのまま放置することで、高額かつ経費化もできない固定資産税の負担がかかり続けることになります。

この記事では、更地の固定資産税について、深堀りして解説します。
3.遊休地を活用するメリット

次に、遊休地を活用するメリットについてご紹介します。
3-1.遊休地を放置するデメリットをすべて解消できる
遊休地を活用することで、前章で解説した、遊休地を放置することで生じるデメリットをすべて解消できる点が、ひとつ目のメリットです。
土地活用を行うことで、土地が荒れたり、ゴミを投棄されたりするリスクはほとんどなくなると言えます。
また、賃貸管理会社により土地が管理されることにもなるため、土地所有者様には管理の手間はかからず、管理コストは土地活用で得られる収益の一部で賄えるようになります。
固定資産税の負担についても、同様に土地活用の収益から賄うことができるようになるだけでなく、必要経費として計上できるようになるため、所得税対策効果も得られます。
特に、土地活用として賃貸住宅経営を行うのであれば、住宅用地の特例を適用できるため、土地の固定資産税は6分の1に軽減することができます。
3-2.収益を得られるようになる
遊休地で土地活用を行うことで、収益が得られるようになる点もメリットです。
遊休地を有効に活用することでデメリットを解消すればマイナスをゼロにすることができますが、さらに収益が得られればゼロをプラスにできます。
お金がかかるだけだった土地が、お金を稼ぐ、働く土地になるということです。

この記事では、儲かる土地活用について解説します。
3-3.節税効果が得られる
遊休地を活用することで、様々な節税効果を得ることができる点もメリットです。
賃貸住宅経営による固定資産税の節税効果については先に触れましたが、その他にも、相続税や所得税の節税効果を得ることもできます。
特に相続税の節税効果は絶大と言ってよく、多くの土地所有者様にとって、土地活用による相続税対策は、一種のセオリーとなっています。
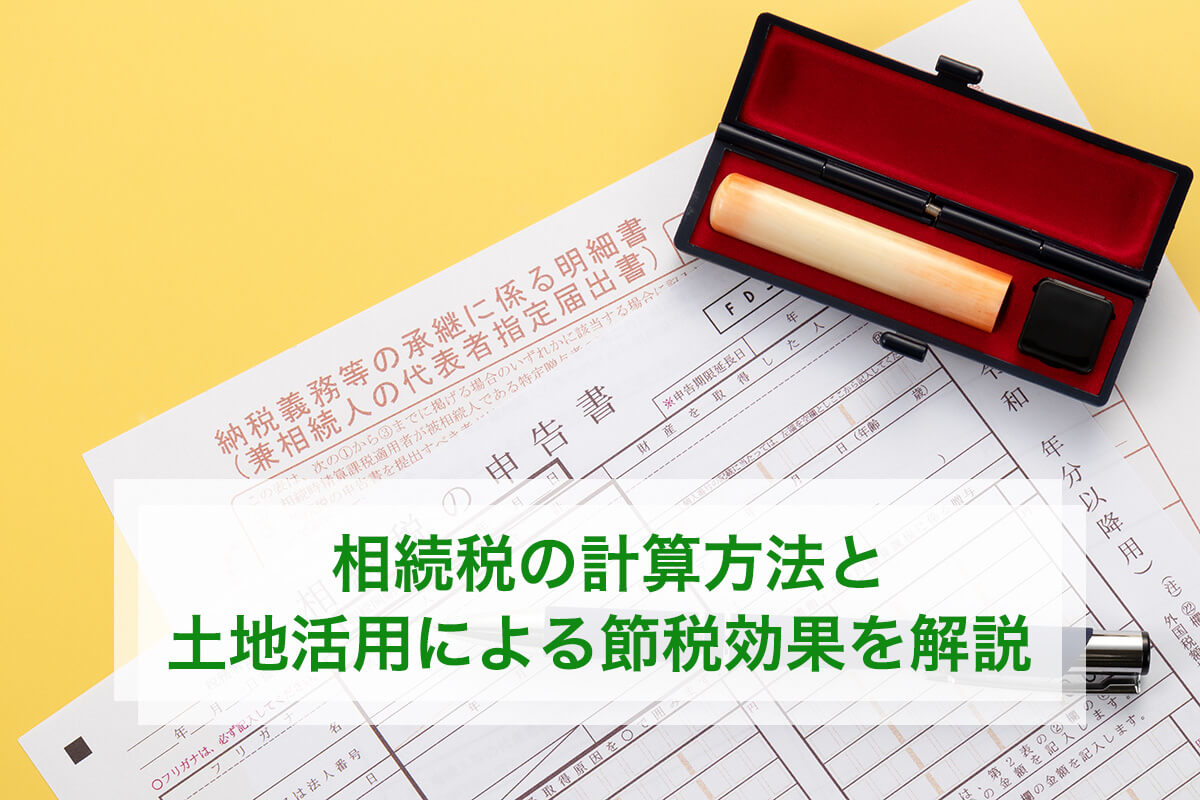
この記事では「相続税」について解説します。
所得税の節税効果については、例えば、オーナー様が会社員で、副業として土地活用を行う場合などに効果的となります。
所得税には、会社員としての給与所得と土地活用の不動産所得を合算して課税所得を求めるというルールがあり、土地活用による不動産所得が赤字の場合は、赤字分を給与所得から控除できます。これを損益通算と言います。
土地活用では、キャッシュフローは黒字であっても、税務上は赤字という状況が生じることがあり、これを利用するのが土地活用による所得税対策です。

この記事では、アパート経営による所得税対策についてご紹介します。
4.遊休地の土地活用方法10選

遊休地で土地活用を行う場合に適した方法として以下の10種類をご紹介します。
- 《 遊休地で有効な土地活用方法 》
- 4-1.賃貸住宅経営
- 4-2.駐車場経営
- 4-3.トランクルーム経営
- 4-4.コインランドリー経営
- 4-5.事業用定期借地権・リースバック方式
- 4-6.資材置き場
- 4-7.自動販売機置き場・駐輪場経営
- 4-8.賃貸併用住宅
- 4-9.貸し農園経営
- 4-10.売却
4-1.賃貸住宅経営
代表的な遊休地の活用方法としては、賃貸住宅経営が挙げられます。
賃貸住宅経営は広いエリアで賃貸需要が見込め、建築規制も厳しくないため多くの土地所有者様が実現できる再現性の高い土地活用と言えます。
また、一定の収益や利回りを確保することができ、安定経営がしやすい点や、節税効果が高い点もメリットです。
節税効果には、住宅用地の特例による固定資産税対策効果や、高い相続税対策効果、損益通算による所得税対策効果も見込めます。
代表的な賃貸住宅経営としては、賃貸マンション経営やアパート経営が挙げられ、主に賃貸マンション経営は都市部で、アパート経営は郊外で行うのに適しています。
土地が狭い場合は、戸建て賃貸経営という選択肢もあります。

この記事では、賃貸住宅特有のメリットやデメリット、法人化の効用などについてご紹介します。
4-2.駐車場経営
駐車場経営は、初期費用がほとんどかからず、基本的にはどんな土地でも始められる点がメリットの土地活用です。
ただし、収益性はあまり期待できず、節税効果については、ほぼないと言えます。
そのため、遊休地を野放しにはできないが、自ら管理するのは難しいため、できるだけお金をかけずに、遊休地を放置するデメリットを解消したいという方におすすめです。
駐車場経営には、月単位で貸す月極駐車場経営と、時間単位で貸すコインパーキング経営の2種類があります。

この記事では、駐車場経営の種類とそれぞれの特徴、収支シミュレーションについて解説します。
4-3.トランクルーム経営
トランクルーム経営とは、個人向けの貸倉庫を経営することを言い、貸倉庫経営の一種です。
貸倉庫には、企業や事業者が商品保管等をする「倉庫業を営む倉庫」と、自分の持ち物を保管したい個人に向けた「トランクルーム」があり、この2つは法的にも別物です。
このうち、遊休地として放置されている土地に適性が高いと思われるのは、トランクルーム経営と言えるでしょう。
トランクルーム経営のメリットは、初期費用が安いことですが、反面、収益性と節税効果が共に低い点がデメリットです。
トランクルーム経営は、賃貸住宅や貸店舗などの需要は少ないながら、住宅街の近くなど、物を保管したいというニーズが見込める立地の場合におすすめの土地活用です。

この記事では、土地活用でトランクルーム経営を行うメリット・デメリットを詳しく解説します。
4-4.コインランドリー経営
コインランドリー経営は、自営に近い土地活用です。
従業員を雇う必要性まではありませんが、店舗の清掃や集金業務は、オーナー様が自ら行うのが一般的と言えます。
コインランドリー経営は、大規模な建物を建築する程の初期費用は必要とせず、経営が軌道に乗れば高い収益性と利回りが期待できるところがメリットです。
反面、経営に手間がかかる点と、経営が上手くいかなかった場合の返済リスクが大きい点がデメリットになります。
コインランドリー経営の場合、融資の返済期間が短いため、返済リスクが大きいのです。
例えば、賃貸住宅経営の場合、30年から40年程の返済期間で融資を組むことができます。
しかし、コインランドリー経営の場合は、民間融資で10~15年、日本政策金融公庫を利用できた場合でも、最長で20年の返済期間となります。
そのため、コインランドリー経営を行う場合は、十分な市場調査を行い、立地の適正をシビアに判断して、失敗を避けることが鉄則と言えます。

この記事では「コインランドリー経営の土地活用」について経営のポイントを5つ解説します。
4-5.事業用定期借地権・建設協力金方式(ロードサイド)
遊休地の活用方法には、企業に対して土地を貸す「事業用定期借地権」や、企業から建設協力金を受けて建物建築して貸す「建設協力金方式(リースバック方式)」もあります。
いずれの方法も、高い収益性と利回りが期待できますが、企業が商売をやりたいと考えるような好立地であることが前提の土地活用方法と言えます。
そのため、基本的に遊休地として放置されている土地にマッチすることは考えにくいです。
しかし、例外的に実現できる見込みのある立地があります。
それが、ロードサイドです。
ロードサイドとは幹線道路や主要な生活道路沿いのことを言い、交通量が多く視認性が高いため小売店やサービス店などの営業に適した立地です。
駅前などの繁華性が高い土地でなくても、ロードサイドに広い土地をご所有されているのであれば、企業を誘致できる見込みがあると考えられます。
特に、ロードサイドに相続した広い実家が残されている土地などの場合、出店担当者の盲点に入っている可能性があります。
このような場合、オーナー様の側から問い合わせをすることで、一気に出店の話が進むケースも少なくありません。

この記事では、ロードサイドの土地の土地活用について解説します。
4-6.資材置き場
資材置き場とは、建築会社などに資材を保管するためのスペースとして土地を貸し出し、賃料を得る土地活用です。
初期費用がかからない反面、収益性と節税効果は共に期待できません。
どちらかというと、賃貸住宅経営等の土地活用方法に適していない場合に、消去法で選択する土地活用と言えます。
資材置き場は、高速道路のインターチェンジに近く、市街地からも遠く離れていない位置にあり、大型車両が出入りしやすい道路に面した、間口の広い土地に向いています。
反対に、住宅地などの場合は、大型車両が頻繁に通行することで近隣住民からクレームを受ける可能性が高いことから、資材置き場の賃貸需要はほとんどないと言えます。
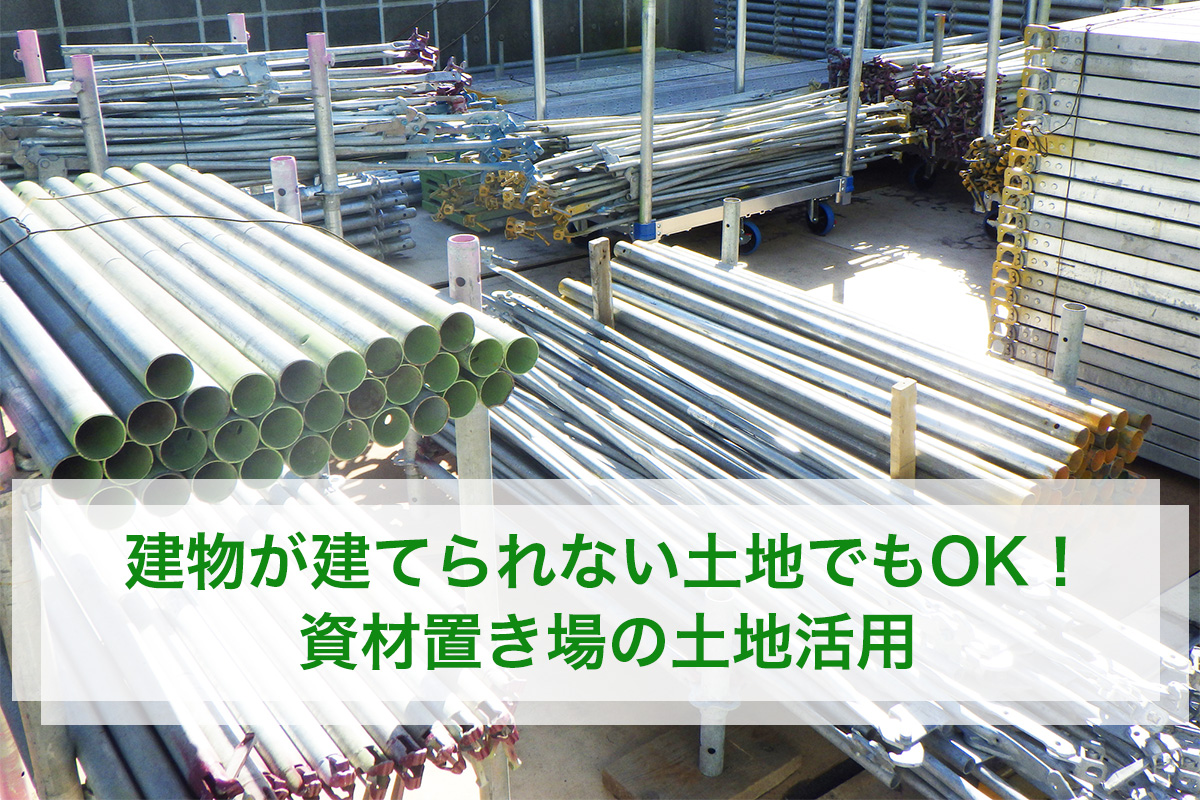
この記事では、建物が建てられない土地でも可能な、資材置き場の土地活用について解説します。
4-7.自動販売機置き場・駐輪場経営
ご所有の遊休地が狭く、活用しにくい土地の場合には、自動販売機置き場や駐輪場経営で活用する方法などが有効と言えます。
自動販売機置き場の運営は、自営で行うこともできますが、管理会社と提携して行う方法を採ることが一般的です。
具体的には、運営業務のすべてを自動販売機管理会社に委託するフルオペレーション方式と、売上金の回収とメンテナンスのみ委託するセミオペレーション方式があります。
駐輪場経営についても、専門会社と協力して行うのが一般的で、駐輪用の設備と料金精算システムを設置するだけで始めることができます。
また、狭い土地や細長い土地のような、使いにくい余った土地を活用する方法は他にもありますので、ご興味のある方は、下記の記事をご参照ください。

この記事では、余った土地を有効に活用する方法について解説します。
4-8.賃貸併用住宅
遊休地に自宅を建築することを視野に入れても良いとお考えの場合は、賃貸併用住宅がおすすめの土地活用となります。
賃貸併用住宅とは、1棟の建物に自宅部分と賃貸部分が共存している、簡単に言えば自宅兼賃貸住宅のことです。
賃貸併用住宅は、自宅部分を含めた建物全体の借入金を、賃貸部分からの家賃収入を使って返済できる点が最大のメリットと言えます。
そのため、マンションの最上階ワンフロアに自宅を構えつつ、実質的な金銭的負担はほとんど生じていないといった状況を作ることができます。
分譲マンションの最上階を購入するより遥かに経済的と言えるでしょう。

この記事では「賃貸併用住宅」の基礎知識について解説します。
4-9.貸し農園経営
農地を相続したものの、営農の後継者がいないという場合には、貸し農園経営で土地活用を行うのも一手です。
農地は、農地法の規制により基本的に農地以外の使い方ができないため、農地のまま土地活用ができる貸し農園経営が有効な選択肢になります。
貸し農園経営といっても、自ら農園を運営する方法以外に、市民農園にして近隣住民に貸し出す方法や、営農者に土地を一括で貸し出す方法もあります。
なお、農地法により、農地は耕作することが原則とされていることから、耕作放棄が続くと、行政からの指導や処分を受ける可能性があるため、注意が必要です。
また、一度荒れてしまった農地を再生するには、多大な労力と費用がかかるため、長期間放置すると、農地として貸すことも難しくなってしまう恐れがあります。
そのため、農地だった土地が遊休地になっている場合は、早めに対策をとることをおすすめします。

この記事では、貸し農園経営による土地活用についてご紹介します。
4-10.売却
遊休地を思い切って売却することも有効活用のひとつと言えるでしょう。
土地を売却すれば、土地所有者様にはまとまった収入が得られます。
ただし、土地を売却するということは、土地を活用する機会を失うことでもあります。
また、遊休地を売ったときに譲渡所得が発生すれば譲渡税がかかります。
譲渡税は、土地の保有期間が5年以内であれば約40%、5年超であれば約20%という高い税率である点が特徴です。
さらに、売却の仲介を不動産会社に依頼すれば、概ね売却価格の3%+6万円の仲介手数料が発生します。
土地を購入する場合も不動産取得税がかかるため、土地を売って現金に換える場合も、現金で土地を買う場合も、基本的に資産は目減りする点に留意する必要があります。

この記事では、活用しないまま土地を売却することが「得策なのかどうか」考えてみます。
ここまで、遊休地に適していると思われる土地活用方法を10種類ご紹介しましたが、土地活用には、他にも様々な方法がありますので、ご興味がある方は、下記の記事をご参照ください。

この記事では土地活用のメリット・デメリットや対策など、土地活用の全体像についての知識をご紹介します。
5.遊休地を活用する際に必要な準備

遊休地を有効に活用するには、以下にご紹介するような準備が必要になります。
いずれも、専門知識が求められるため、基本的には、土地活用の専門会社に依頼して、準備を進めるようにしましょう。
5-1.整地費用の見積もりを取る
遊休地に凹凸があったり、傾斜していたりすると、整地が必要になります。
整地費用は、土地活用を行う際の初期費用に加わるため、適切な事業計画を検討するうえで必要な情報となります。
土地活用の方法を決める前に、整地費用が大体いくらくらいになるのか、工事業者に見積もりを取っておくようにしましょう。
整地費用にいくらかかるかを確認することで、整地費用を含めても十分な収益を出せる土地活用の計画を検討することができます。
また、傾斜地などの場合は整地費用が高額になりやすいため、傾斜地のまま建物を建てる方法なども検討する余地があります。
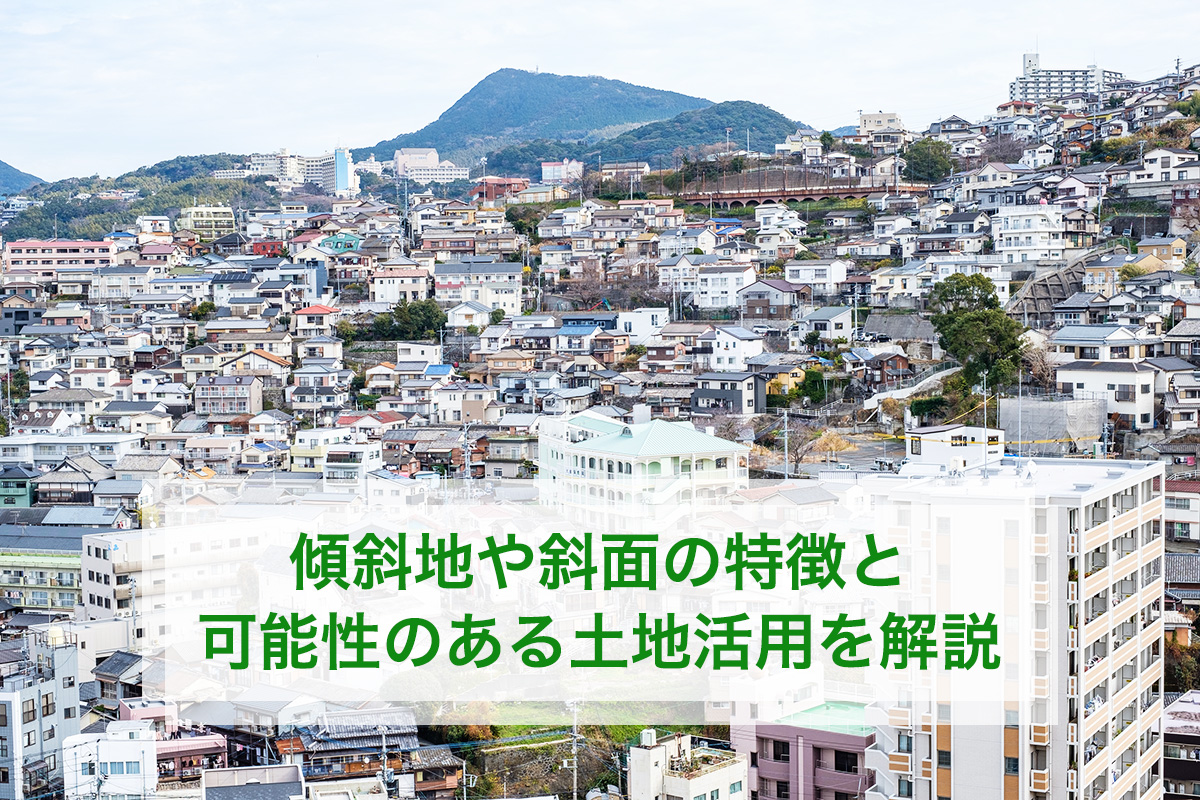
この記事では、「傾斜地や斜面の土地活用」について解説します。
5-2.賃貸需要を確認する
土地活用には様々な種類がありますが、失敗しないためには、所有する遊休地に合った方法を選択することが重要と言えます。
ご所有地に合った土地活用とは、賃貸需要が見込める土地活用です。
賃貸需要を調べるためには、土地活用の専門会社に市場調査を実施してもらうことで、正しい情報が確認できます。

この記事では、土地活用に欠かせない市場調査の方法や土地別の人気土地活用をご紹介します。
5-3.遊休地の広さ・形を正確に確認する
遊休地の広さや形を確認することも大切です。
何世代も相続されてきた遊休地の場合、実際の土地面積と登記簿に記載されている土地面積が異なる場合があるためです。
土地活用のプランニングでは、土地に対してどのように建物や駐車場等を配置するかを決める図面を作成する必要があるため、土地の正確な面積や形状を確認することは極めて重要と言えます。
遊休地の広さや形を確認するには、土地活用の専門会社に現況測量をしてもらい、敷地図面を作成してもらう方法があります。
土地の広さによっても、適した土地活用の方法が異なりますので、測量により正確に確認するようにしましょう。
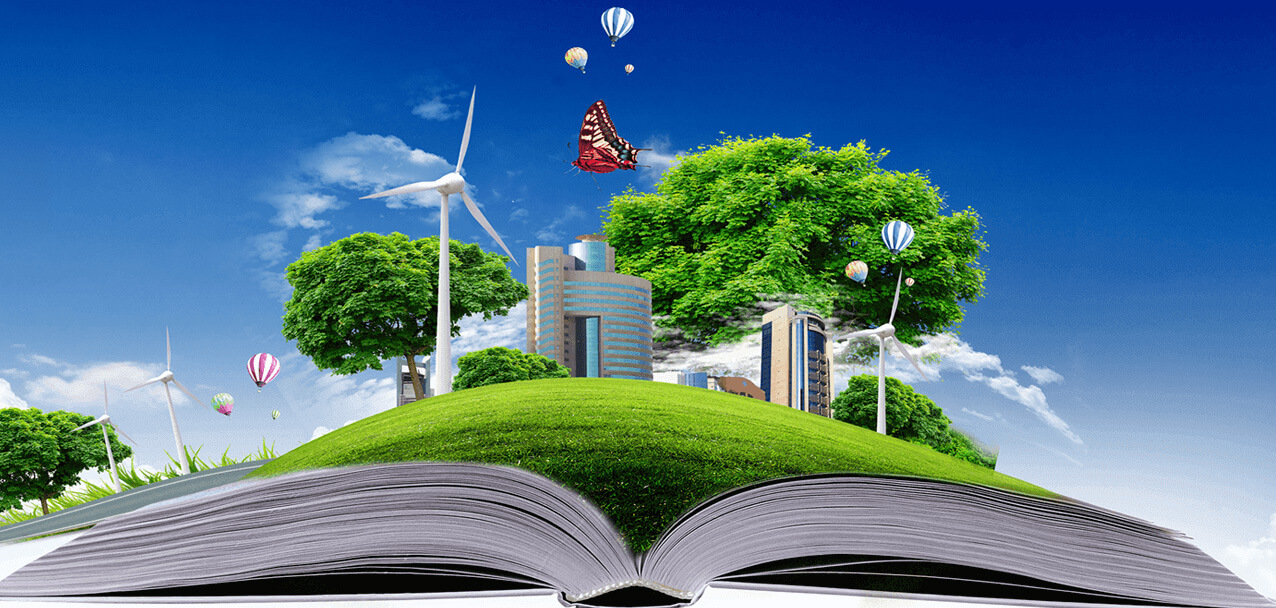
土地活用や節税などに関する情報を分かりやすく解説する、東建コーポレーションの「土地活用の記事一覧」です。
5-4.建築法規を確認する
遊休地にかかっている法規条件を確認することも大切です。
その理由は、土地が所在するエリアによって、建てられる建物の用途や規模を定める法規制が存在しているためです。
例えば、「用途地域」の規制では、建築可能な建物の用途を、13種類のエリアに分類して定めています。
また、土地の敷地面積の何%までを建物の建築面積として良いかを定める「建ぺい率」や、敷地面積の何%まで建物の延べ床面積を確保して良いかを定める「容積率」という建築法規もあります。
こうした規制は、建築基準法や都市計画法により定められていますが、これらの建築法規をすべて把握するのは困難であるため、土地所有者様が自ら調査する必要はありません。
そのため、一級建築士が所属する土地活用の専門会社に相談して、調査を任せるのが確実と言えます。

この記事では、土地活用に関係が深い用途地域について解説します。

この記事では、容積率200%の土地を有効活用するための方法を解説します。
6.遊休地を放置するデメリットと有効活用する
メリット まとめ

以上、遊休地を放置するデメリットと有効活用するメリットを解説しました。
遊休地とは、あらゆる用途にも活用されずに放置されている土地のことでした。
遊休地を放置するデメリットには、「土地が荒れ、ゴミが散乱する恐れがある」ことや、「管理をする手間やコストがかかる」こと、「高額で経費化できない固定資産税の負担が生じ続ける」ことがありました。
遊休地を活用すれば、「遊休地を放置するデメリットが解消される」ことをはじめ、「収益を得られるようになる」、「節税効果が得られる」というメリットがありました。
遊休地を活用する具体的な方法としては、「賃貸住宅経営」をはじめとした10種類の土地活用をご紹介しました。
遊休地を活用するポイントとしては、「整地費用の見積もりを取る」、「賃貸需要を確認する」、「遊休地の広さ・形を正確に確認する」、「建築法規を確認する」が挙げられ、いずれも専門知識を要するため、土地活用の専門会社にご相談することをおすすめしました。
東建コーポレーションは土地活用の専門会社として全国で地域密着の土地活用コンサルティング業務を実施し、土地活用の実績やノウハウを積み上げてきました。
遊休地を有効に活用する際には、その土地に合った、賃貸需要が見込める土地活用方法を選ぶことが非常に重要です。
遊休地の活用方法についてお悩みの際は、ぜひ東建コーポレーションへ、お気軽にご相談ください。





 PAGE TOP
PAGE TOP



